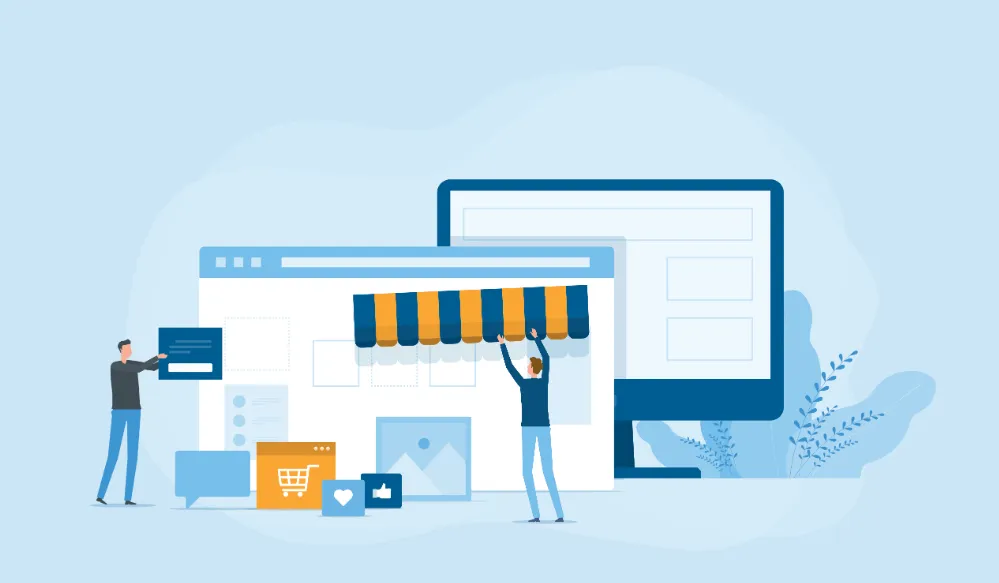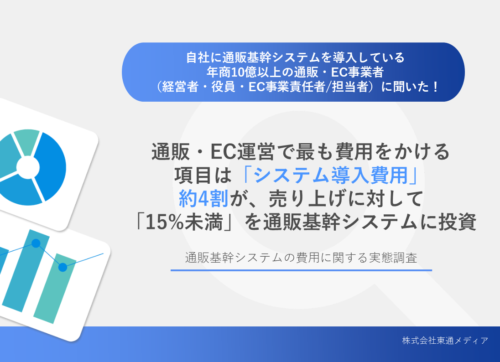ECサイトの月商が数百万円を超え、独自機能の追加やシステム連携の必要性が高まり、より柔軟なECプラットフォームへの移行を検討する企業が増えています。
しかし、フルスクラッチ開発では数千万円の初期投資が必要となり、パッケージ型でも専門人材の確保が課題となります。
そこで注目されているのが、初期費用を抑えながら高い拡張性を持つ「クラウドEC」です。
本記事では、クラウドECの仕組みや特徴をはじめ、ASP・パッケージ型・フルスクラッチとの違い、導入費用の相場、具体的な導入ステップまで徹底解説します。
業界注目のクラウドECとは?仕組みや特徴
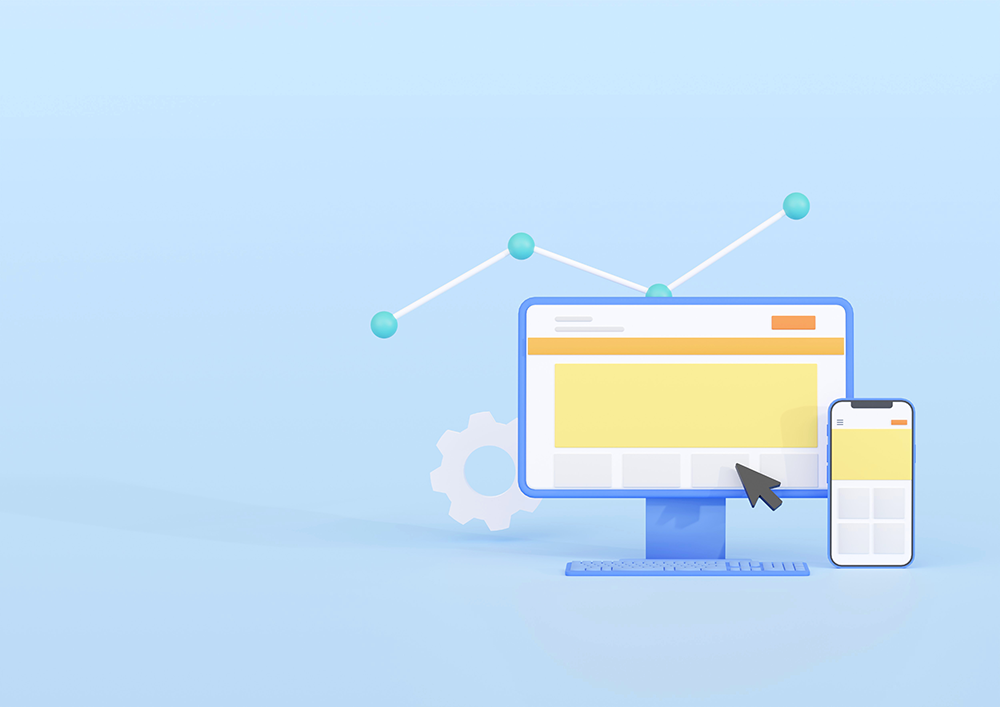
クラウドECとは、クラウド上にECを構築できる仕組みを提供するシステムのことです。
インターネット上のクラウド基盤を活用してECサイトを構築・運用する方式で、従来のオンプレミス型(サーバーなどのインフラを自社で導入・運用)とは異なり、サーバーの管理やインフラ整備が不要となります。
中小企業のDX推進を後押ししている点も特徴的で、システムの柔軟性と拡張性により、事業成長に応じた機能追加が容易になっています。
クラウドECの特徴
クラウド基盤で短期間にECを公開できる仕組みが、クラウドECの最大の特徴です。最短で数週間から1ヶ月程度での立ち上げが可能となり、スピーディな市場参入を実現できます。
クラウドECの主な特徴を整理すると、次のような点が挙げられます。
- システムの柔軟性と拡張性により、事業成長に応じた機能追加が容易
- 初期投資を抑えながら高機能なECサイトを短期間で立ち上げ可能
- 専用のサーバー環境を用意することなく、インターネット経由で構築・運営
- ベンダー側がインフラ管理を担うため、IT専門人材が不要
導入にあたっては自社の事業規模や将来的な成長戦略を十分に検討し、適切なサービス選定が欠かせない点に注意が必要です。
ただし、カスタマイズの自由度には一定の制限があるため、独自性の高い機能を求める場合は、パッケージ型やフルスクラッチ型との比較検討が必要です。
導入によるメリット
初期投資を抑えてすぐに稼働を始められることが、クラウドEC導入の最大のメリットです。従来のパッケージ型よりも初期費用や運用費用を大幅に削減できます。
企業がクラウドEC導入で得られる具体的なメリットは、以下の通りです。
①初期投資の大幅な削減
②セキュリティ対応をベンダーに任せられる
- PCI DSS準拠
- SSL証明書の管理
- 不正アクセス対策を専門家に委託
③保守作業を減らして運用負担を軽くできる
- サーバーメンテナンス不要
- バックアップ作業の自動化
- システムアップデートの自動適用
④越境ECなど新しい市場へ進出できる
- 多言語・多通貨対応
- 海外市場への参入が容易
キャンペーンサイトを立ち上げるなど、機動的なマーケティング施策も実現可能です。スケーラビリティの高さにより、アクセス集中時も自動的にリソースを拡張し、安定したサービス提供が可能となります。
導入前に押さえたいデメリット
高度なカスタマイズに制約が発生してしまうことは、クラウドECの最大のデメリットです。独自の業務フローや特殊な商品管理が必要な場合、標準機能では対応しきれないケースがあります。
導入前に認識しておくべき主要な課題を、以下にまとめました。
【システム面の制約】
①高度なカスタマイズの限界
- 独自の業務フローへの対応が困難
- 特殊な商品管理機能の実装に制限
②システム依存で乗り換えが難しい
- データのエクスポート機能の確認が必要
- 移行サポートの有無を事前確認
【運用上のリスク】
①通信障害時にサービスが止まる可能性
- インターネット接続が前提
- ネットワークトラブルで完全停止のリスク
②法規制や外部送信規律への対応
- 特定商取引法、景品表示法への準拠
- 個人情報保護法の要件
- 2023年6月施行の外部送信規律
これらのデメリットを十分に理解した上で、リスクヘッジの方策を事前に講じておくことが、導入成功への重要なポイントとなります。
クラウドECとASPの違いを比較【選び方のポイント】

ECサイト構築には、クラウド型、ASP型、パッケージ型、フルスクラッチ型などの方法が存在します。
提供形態の違いを理解して判断できるようにすることが重要で、それぞれに初期費用やランニングコスト、構築期間が大きく異なります。
| 構築方法 | 初期費用 | ランニング費用 | 構築期間 |
| ASP型 | 0~10万円 | 月額0.5~5万円 | 即日〜1ヶ月 |
| クラウド型 | 100~500万円 | 月額10~50万円 | 1~3ヶ月 |
| パッケージ型 | 500万円~ | 月額20~100万円 | 3~6ヶ月 |
| フルスクラッチ型 | 3000万円~ | 月額50万円~ | 6ヶ月~1年 |
※費用は一般的な相場であり、要件により変動します
費用と運用体制の差を把握して選択を進める必要があり、自社のビジネスモデルや成長戦略に応じた選択が求められるでしょう。
どの方式を選択するにせよ、将来的な事業拡大を見据えた長期的視点での検討が不可欠となります。
ASP型ECの特徴
低コストで導入を始められる利点があるASP型ECは、Application Service Providerの略称で、インターネット経由でECサイト機能を提供するサービスです。
【ASP型ECの基本情報】
- 初期費用:無料~数万円程度
- 月額料金:数千円から利用可能
- 代表的サービス: BASE、STORES、Shopifyなど
しかし、機能が限定されて成長段階で壁が生じてしまうことは避けられません。ASP型の制約として以下の点が挙げられます。
- デザインのカスタマイズがテンプレートベースに限定される
- 独自機能の追加が困難である
- 月商数百万円超で手数料負担が重くなる
- B2B取引や定期購入への対応が難しい
ASP型からの移行を検討する企業の多くは、この成長の壁にぶつかったケースが大半を占めています。拡張性が限られて柔軟な対応が難しくなる点も、事業成長の制約となります。
ASP型は初期段階では有効な選択肢ですが、中長期的な成長戦略を描く企業には、より柔軟性の高いシステムへの移行タイミングを見極めることが重要です。
パッケージ型ECの特徴
自由度の高い構築を実現できる利点があるパッケージ型ECは、ECサイトに必要な機能をパッケージ化したソフトウェアを購入・導入する方式です。
【パッケージ型ECの概要】
- 主要サービス:ecbeing、通販マーケッターEight!、Commerce21など
- 採用企業層:中堅から大手企業
- 初期費用:500万円~数千万円
- 適正規模:年商数億円規模
大規模開発に適する一方で、費用が高騰してしまう特徴があります。また、以下のように「保守や運用に専門人材が欠かせなくなる点」も考慮すべきです。
- システム管理者やエンジニアの常駐
- 外部ベンダーとの保守契約
- 年間数百万円の維持費
- 継続的なバージョンアップ対応
さらに、サーバー費用やライセンス料、保守費用などのランニングコストも考慮する必要があり、年間の維持費は数百万円に達することも珍しくありません。
とはいえ、大規模な取引量や複雑な業務要件がある企業にとっては、投資に見合う価値を提供できるシステムといえます。
フルスクラッチ型ECの特徴
独自仕様に完全対応できる開発を行えるフルスクラッチ型ECは、ゼロからオーダーメイドでシステムを開発する手法です。
自社の業務フローに100%適合したシステムを構築でき、競合他社との差別化を図る独自機能の実装も自在に行えます。
大手ECサイトの多くがこの方式を採用しており、ユニークなユーザー体験を提供できるでしょう。
費用と期間が大きく膨らんでしまう特徴があることは避けられません。開発費用は最低でも数千万円、大規模なプロジェクトでは億単位の投資が必要となり、開発期間も半年から1年以上を要します。
長期的な運用でROIを確保する必要が生じる点も重要です。開発後の保守運用コストも莫大で、専任のエンジニアチームが不可欠となります。
導入コストと運用体制の違い
クラウドECは低コストで月額制を利用できる特徴があります。各方式のコスト構造と運用体制の違いを理解することで、適切な選択ができるでしょう。
構築方式ごとの費用特性は、以下の通りです。
- ASP型:初期費用は数万円程度
- クラウドEC:初期費用100万円前後、月額10万円~
- パッケージ型:初期投資500万円以上
- フルスクラッチ:数千万円規模の予算確保が必要
運用体制も社内か外注かで違いが出てきます。クラウドECやASP型では、ベンダー側がインフラ管理を担うため、社内にIT専門人材を配置する必要がありません。マーケティングやコンテンツ制作に人的リソースを集中できる点は大きなメリットでしょう。
対照的に、パッケージ型やフルスクラッチ型では、システム管理者やエンジニアの常駐が前提となります。
セキュリティや法規制への対応差
クラウドECは国際基準に準拠しやすくなっている点が特徴です。国際的なセキュリティ基準であるISO27001やPCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)への準拠がベンダー側で整備されており、最新のセキュリティ脅威への対応も迅速に行われます。
サーバーやアプリケーション、ネットワークといったインフラを自社内で導入・運用するオンプレミス型の場合、自社で更新や監査を担う必要があります。セキュリティ監査や脆弱性診断、インシデント対応体制の構築など、専門知識と継続的な投資も求められるでしょう。
また、ECサイト運営においては、個人情報保護法や外部送信規律に対応しなければならない点も重要となります。
2023年6月に改正された法規制への対応状況は、以下の通りです。
- Cookie利用の同意取得義務化
- プライバシーポリシーの整備
- 外部送信規律への準拠
- 特定商取引法の表示義務
クラウドECではこれらの法改正への対応もベンダーがサポートしますが、最終的な責任は事業者にあることを忘れてはいけません。適切なベンダー選定と継続的な法令遵守体制の構築が、事業継続の大前提となります。
自社に最適なサービスを選ぶ判断基準

事業規模に応じたサービスを選定できるようにすることが、EC成功の第一歩です。適切なサービス選択のために、以下の4つの判断基準を検討する必要があります。
【4つの判断基準】
①事業規模による選定
- 年商1億円未満 → ASP型
- 年商1億円以上 → クラウドEC
- 年商10億円超 → パッケージ型/フルスクラッチ型
②ITスキルと運用体制
- エンジニア不在 → クラウドEC/ASP型
- IT部門あり → パッケージ型も検討可
③長期的なコストと拡張性
- TCO(総保有コスト)で比較
- 将来の機能拡張の可能性を考慮
④法規制とセキュリティ基準
- 特定商取引法、景品表示法への対応
- 個人情報保護法の要件充足
- PCI DSS準拠の必要性
多くの企業が身の丈に合わないシステムを導入し、運用負荷に苦しむケースが散見されます。自社の現状と将来像を明確にし、段階的な成長戦略を描くことが重要です。
最初から完璧なシステムを求める必要はなく、事業成長に応じて柔軟に拡張できるシステムを選択することが、長期的な成功につながるでしょう。
クラウドEC導入にかかる費用とサポート体制

費用相場を理解して予算を組むことが、導入検討の第一歩となります。クラウドEC導入には、初期費用と月額費用の両方を考慮する必要があり、トータルコストの把握が重要です。
導入後のサポート内容を確認して安心できる体制を整えることも欠かせません。24時間対応、専任担当者制、定期レビューなど、ベンダーごとにサポート体制には大きな差があるため、事前の確認が必要でしょう。
また、補助金を活用して投資負担を軽くできる可能性もあるため、補助金や助成金などの情報収集は欠かせません。
初期費用と月額費用の目安
クラウドECの初期費用は100万円~数百万円になることが多いのが実情です。この金額には、基本システムの設定、デザインテンプレートのカスタマイズ、商品データの移行作業などが含まれます。
月額利用料は10万円以上が相場となっており、基本プランでも10万円から30万円程度が標準的です。
【導入費用の概要】
- 初期費:100万円~500万円程度
- 月額費用:10万円~50万円程度
- 追加開発:システム連携などで数百万円の場合も
スモールスタートをしても、拡張機能・デザイン強化で費用が跳ね上がることに注意が必要です。トランザクション数やストレージ容量、アクセス数により従量課金が発生するケースが多く、事業規模の拡大とともにコストが増加します。
追加オプションやシステム連携なども考慮し、予算見積もりを慎重に取るべき点も重要です。
初期段階では最小構成でスタートし、売上成長に応じて機能を追加していく段階的な投資計画が、リスクを抑えた賢明な選択といえるでしょう。
クラウドEC導入を成功させる実践ステップ
クラウドECを導入するにあたり、要件定義から公開まで順序立てて進めることが大切です。
実践ステップの例を、以下の表にまとめました。
| ステップ | 内容 |
| ①導入目的とKPIを明確にする | ・売上拡大や効率化の目的を定義して進める ・KPIを設定して進捗を定量的に把握していく ・目的が曖昧だと失敗につながってしまう |
| ②プロジェクト体制と担当者を決める | ・責任者と担当範囲を明確にして管理していく ・外部パートナーとの連携体制を整えて進める ・小規模でも運用責任を一本化して進める |
| ③商品データ・顧客データを整備する | ・商品情報を統一フォーマットに整理して登録する ・顧客データを正確に移行してCRMを活用する ・PIMなどの専用ツールを導入して効率化する |
| ④既存システムや外部サービスと連携させる | ・在庫や会計システムと連携して効率化を進める ・APIを活用して外部サービスと接続を行う ・連携不備がトラブルにつながることを防ぐ |
| ⑤セキュリティ・法令対応をチェックする | ・特商法や景表法の表示義務を確認して対応する ・個人情報保護法や外部送信規律に準拠して運用する ・PCI DSSやPマークなど認証を参考にして導入する |
| ⑥運用フローを標準化して効率化する | ・受注から配送までの手順を定義して整える ・担当者ごとの役割を分担して可視化していく ・マニュアル化して属人化を防いでいく |
| ⑦SEO・SNS・広告など集客施策を実行する | ・SEO対策で検索流入を安定的に確保していく ・SNS運用で認知を広げて顧客接点を増やしていく ・広告を活用して短期的な集客を補完していく |
| ⑧効果測定と改善サイクルを回す | ・アクセス解析で施策の成果を数値化していく ・PDCAを回して改善を継続して行っていく ・継続改善で売上と顧客体験を高めていく |
多くの企業が陥りがちな失敗は、準備不足のまま導入を急ぐことです。
データ移行とテストを経て安定運用が始まり、公開後は改善や集客施策を継続して実行することで、持続的な成長を実現できるでしょう。
クラウドECの導入事例

クラウドECを検討するにあたり、導入事例を参考にすることも大切です。ここで取り上げる事例から、成功のポイントと課題解決のアプローチを学べるでしょう。
【クラウドEC導入企業】
- 株式会社戸村精肉本店
- リンガーフーズ株式会社
- 株式会社カワダ
- 株式会社フレネットHIBIYA
- 株式会社グループセブ ジャパン
- 西川株式会社
各社が直面した課題や解決方法は様々で、自社の状況に近い事例を参考にすることが重要となります。
株式会社戸村精肉本店
宮崎県に根ざし、スーパー4店舗運営、レストラン、自社食肉加工工場を持つ株式会社戸村精肉本店は、クラウドECを導入し、宮崎の名産品である焼肉のたれやドレッシングを全国に届ける体制を構築しました。
以前のサイトでは商品の見せ方が固定的で、画像や説明文の配置が限られており、キャンペーンや新商品をタイムリーにアピールできないという課題を抱えていたそうです。
また、県外への販路拡大にも限界を感じ、送料負担に見合う商品価値の訴求が必要でした。
【導入による成果】
- コンバージョン率が約1.3%から4%へ向上
- 売上高が昨年同月比130%を達成
- 注文処理が自動化され、一件あたり5~10分かかっていた作業が効率化
導入後は全国からの注文が増加し、特に東京より北の地域からの注文が増えました。
さらに、期間限定の価格変更や会員ランクごとの割引設定が自動化され、運営負担が大幅に軽減されています。
リンガーフーズ株式会社
リンガーハットグループの外販事業を担うリンガーフーズ株式会社は、冷凍ちゃんぽんや皿うどんをメインに展開しています。
旧サイトは商品を販売するのみのカートシステムで、様々な施策を実施する機能がなく、はがき・FAX注文が多いため運用効率化も課題でした。社内のDXチームからクラウドECを紹介され、操作性と機能性の高さから採用を決定しました。
【導入による成果】
- 単月売上前年対比が最大215%アップ
- サイト会員数が1.5倍に増加
- かご落ち分析で的確な対策が可能に
新聞の折り込みチラシや会員へのDMはがきにQRコードを掲載し、紙媒体からECサイトへの移行を促進するとともに、店舗でのPOPチラシにもQRコードを掲載し、ECサイトの認知拡大を推進しています。
業務効率化も実現し、ユーザー管理、受注業務、商品管理が効率的になりました。
株式会社カワダ
70年以上にわたりブロック玩具や知育玩具を手がける株式会社カワダは、玩具メーカーであると同時に国内外約300社の商品を取り扱う問屋として事業を展開しています。
2009年からBtoB向けECを開始し、2013年にクラウドECを導入しました。2022年にBtoBに特化した大幅なサイト改修を実施し、法人顧客がより注文しやすいECサイトへと進化させました。
【一括注文機能による成果】
- 平均注文単価が約3万円から5万円に(約1.6倍)向上
- 受発注処理が6〜8倍効率化
- 契約締結期間を通常3〜6か月から最短2営業日に短縮
商品リストをアップロードすればまとめて注文できる一括注文機能により、エクセルで在庫管理する法人顧客の利便性が大幅に向上しています。
また、新製品の予約注文にも対応し、リピーター獲得や月次の売上予測がしやすくなりました。
株式会社フレネットHIBIYA
生花や鉢物、資材といった花にまつわる総合仲卸として、東京・大阪・福岡の市場に拠点を持つ株式会社フレネットHIBIYAは、「ハナノヒmarket」(旧・百花市場)というマーケットプレイス型ECサイトを運営しています。
生産者が直接ユーザーへ販売できる仕組みを構築し、生産者の販売チャネル拡大を支援しています。
以前のフルスクラッチサイトは拡張性がなく、セキュリティ対策やスマホ対応に課題があり、クラウドECを導入しました。
【システム移行による効果】
- 30~40%程度の工数削減を実現
- ランニングコストの削減により他の施策への予算配分が可能に
- CMSによる更新作業の効率化でタイムリーな情報発信
現在は法人と個人の割合が8対2で、日比谷花壇をはじめ大手量販店やフラワースクール講師が主な顧客です。
市場の買参権を持たない方や市場に来られない方にECサイトを案内し、以前必要だった取引契約書の締結が不要になったことで、新規顧客獲得が容易になっています。
株式会社グループセブ ジャパン
フランス発の調理器具・小型家電ブランド「ティファール」を展開する株式会社グループセブ ジャパンは、クラウドECを導入し、従来別々に運営していたブランドサイトと公式オンラインストアを統合した新たな「ティファール公式サイト」をオープンしました。
最大の課題は、トラフィックがブランドサイトとECサイトに分散し、SEO効果の分散や管理の煩雑さでした。また、SNSから購買への動線が不十分で、グローバル本社から提案されるプラットフォームは日本の商慣習(複雑な郵便番号システムや送料体系)に対応できないという問題もありました。
【日本市場へのローカライズ成果】
- ブランドサイトとECサイトの統合でSEO効果を集約
- 日本独自の決済・配送システムに対応
- マーケティング部門との連携が格段に円滑化
今後は実店舗との連携強化を目標とし、OMO(Online Merges with Offline)の実現を目指しています。
西川株式会社
創業1566年の歴史を持つ寝具メーカーの西川株式会社は、クラウドECを導入し、サブスクリプション形式で寝具を提供するサービス「Sleep Charge(スリープチャージ)」を2021年9月に開始しました。
エアーマットレスは使用満足度が高いものの、新規顧客が購入に至るまでのハードルが高いという課題がありました。実店舗で寝心地を試せても、日常生活での効果までは実感できないため、自宅で体験できるサブスクモデルを構築しました。
【サブスクモデルの成果】
- 「お試しコース」から3割以上が継続利用や新品購入へ移行
- 従来の販売チャネルとは異なる若い年齢層の開拓に成功
- 複数商品を試してから購入するケースが多いことを発見
物流コストやリユース品のクリーニングなど、モノのサブスク特有の課題を協業先企業との連携により克服しています。
クラウドECの最新トレンドと今後の展望

ヘッドレスコマースが普及して柔軟性が高まる時代を迎えています。フロントエンドとバックエンドを分離することで、より自由度の高いユーザー体験の提供が可能となりました。
また、越境EC市場が拡大しており、海外販路が重要になっています。
法改正が強化され透明性と信頼性が重視される流れも加速しており、2023年の外部送信規律施行に続き、今後もプライバシー保護やサステナビリティに関する規制強化が見込まれます。
中小企業のDX推進を加速させる主要手段として位置づけられているクラウドECは、地域経済の活性化にも貢献しています。変化を恐れずに新しい取り組みにチャレンジする姿勢が、今後のEC事業成功の鍵を握るでしょう。