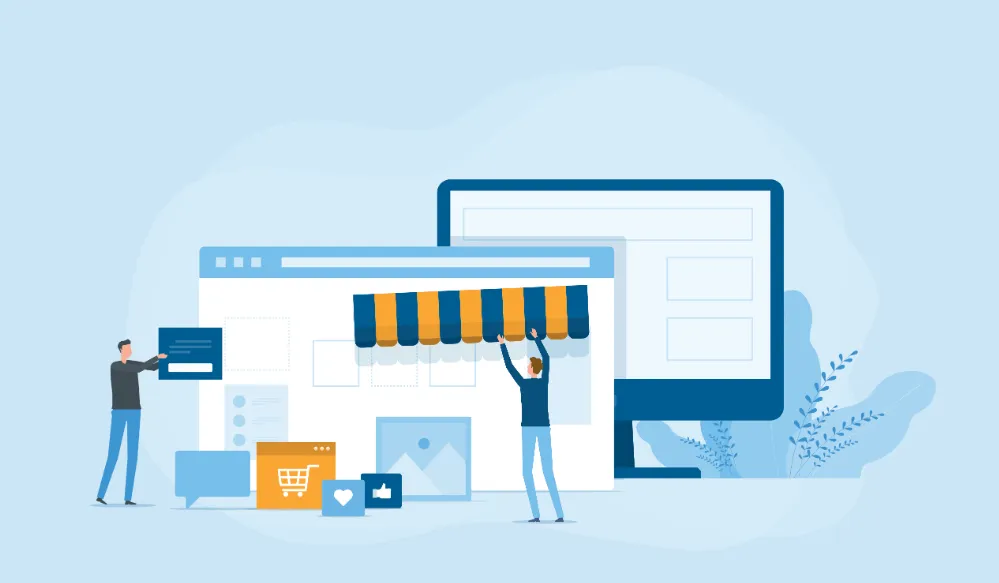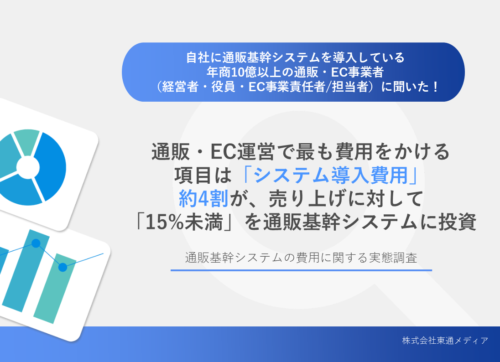これからEC事業に参入したい、あるいはEC事業を拡大したい中小企業にとっては、ECサイト制作や構築にかかるコストが大きな負担になる可能性もあります。
しかし、ECサイトを立ち上げることで、販路拡大・売上アップ・業務効率化といったメリットが得られることも事実です。
そこで本記事では、ECサイト構築に使える補助金制度である「中小企業省力化投資補助金」について、制度の概要や申請要件、申請手続きなどを詳しく解説します。
中小企業省力化投資補助金とは?

中小企業省力化投資補助金は、2024年度補正予算により創設された新しい補助金制度です。経済産業省(中小企業庁)が所管し、人手不足に直面する中小企業の設備導入やシステム構築を支援します。
この補助金では、IoTやロボットなど省力化に資する投資の費用の一部を国が補助し、企業の生産性向上と賃上げを実現することを目的としています。
具体的には、中小企業が業務効率化や自動化に取り組む際の初期投資負担を軽減し、売上拡大や付加価値向上につなげる狙いがあります。
また、本制度は従来の事業再構築補助金を発展・再編して創設されたものであり、2023年度までの大型補助金の性格を引き継ぎつつ予算規模が縮小されています。
なお、カタログ掲載製品を導入する「カタログ注文型」と、自由な設備・システム導入に対応する「一般型」の2種類が設けられており、それぞれ申請方法や補助上限額などが異なります。
制度の概要
制度は大きく「カタログ注文型」と「一般型」の2類型に分かれています。
| 項目 | カタログ注文型 | 一般型 |
| 主な導入方式 | ・事務局が作成したカタログに掲載されている汎用的な省力化製品を導入 ※省力化効果が認められた製品リストから選定 |
・各企業のニーズに合わせたオーダーメイドの設備投資やシステム構築 ※独自仕様や高度な省力化など幅広く対応 |
| 申請受付スケジュール | ・随時受付(いつでも申請可) ・比較的短期間で採択結果が出る |
・年に数回の公募期間が設定され、その都度申請・審査・採択から交付決定まで数ヶ月要する |
| 補助上限額 | ・従業員規模に応じて最大1,500万円 (賃上げ要件達成で上限引き上げ) |
・最大1億円 (従業員101名以上+大幅賃上げ特例時) |
| 補助率 | ・1/2が基本 | ・中小企業1/2 ・小規模・再生事業者2/3 |
| 特徴 | ・カタログ掲載製品を選ぶため導入ハードルが低い ・省力化が即実感できるツール導入に向く ・審査プロセスが簡易で採択まで短い |
・課題や要望に合わせて投資計画を自由に構築 ・大規模・高度な設備やシステム導入に対応 ・交付決定まで期間はかかるが上限額が非常に大きい |
| 審査・交付決定期間 | ・必要書類を提出後、書類審査 ・採択通知が早ければ1ヶ月ほど ・採択後の交付決定を経て導入開始 |
・公募締切後に審査、採択通知まで数ヶ月 ・採択→交付決定後に投資着手 ・事業期間は最長12~18ヶ月程度が多い |
| 想定導入例 | ・清掃ロボット、無人搬送車 ・自動券売機など汎用機器 ・省力化製品を手軽にセット導入 |
・ECサイト構築、独自のシステム開発 ・工場向けAI画像検査装置 ・自動梱包機や高度な物流システム |
| 申請に向く企業像 | ・小~中規模事業者で省力化ツールを素早く導入したい ・比較的低コストで省人化を進めたい |
・オーダーメイドの大型投資を検討している ・余裕をもって審査 ・交付決定を待てる ・大幅な省力化や賃上げ特例を狙う企業 |
※2024年度開始の新制度につき、詳細は今後変更される可能性があります
※最新情報は経済産業省 中小企業庁や事務局サイトでご確認ください
※補助率・上限額は賃上げ計画の有無や企業規模により変動します
カタログ注文型は省力化効果が認められた汎用的な製品を事務局のカタログから選んで導入する方式で、随時申請を受け付けており、比較的短期間で採択結果が得られます。
一方、一般型は各企業の課題に合わせたオーダーメイドの設備投資やシステム構築を対象とし、年数回の公募期間中に申請を行う方式です。
出典:経済産業省「担当者に聞く「より活用しやすく! 令和7年中小企業省力化投資補助金のポイント」」
補助対象となる投資例
補助対象となる投資の種類は非常に幅広く、工場や店舗・オフィスにおける各種の省力化設備から業務用ソフトウェアまで多岐にわたります。
たとえば、カタログ注文型で導入が想定されているものには、無人搬送車(AGV)や自動倉庫システム、券売機、清掃ロボット、調理の自動化装置など、労力を削減できる汎用機器が含まれます。
また一般型では、企業ごとの業務プロセスに合わせたオーダーメイドの装置・システム開発も対象です。例えば、製造業でAIカメラを用いた自動外観検査装置を現場に合わせて導入したり、通信販売(EC)事業で自動梱包機と倉庫管理システムを新規開発して導入するといったケースが想定されています。
このように、人手不足解消や効率化に資する設備投資であれば、ハード・ソフトを問わず幅広く補助対象となる点が特徴です。
中小企業省力化投資補助金でECサイトを制作するメリット

ECサイトの構築は、中小企業にとってデジタル化・販路拡大の大きな一歩ですが、開発費用や運用負担の大きさが課題となりがちです。
中小企業省力化投資補助金を活用すれば、その初期費用負担を大幅に軽減でき(補助率1/2〜2/3)、さらにEC導入による業務効率化や売上拡大の効果で投資対効果を高めることができます。
補助金の後押しによって、従来は高額な投資ゆえに断念していたオンラインショップ構築にもチャレンジしやすくなり、人手不足の解消や新規顧客層の開拓といった恩恵も受けられるでしょう。
ここからは、補助金を活用してECサイトを制作するメリットを解説します。
ECサイト制作費用の大幅な負担軽減
ECサイト制作には、サイトデザイン費やシステム構築費、決済機能の導入などで多額の費用がかかることがあります。規模にもよりますが、数百万円単位の初期投資が必要となるケースも珍しくありません。
しかし、中小企業省力化投資補助金を活用すれば、その費用の半分(50%)は国の補助でまかなうことができます(小規模企業等の場合は2/3まで補助率引き上げ)。
たとえば、従業員10名程度の企業が500万円のECサイト構築費用を計画している場合、通常なら最大250万円の補助金を受けられます(賃上げ要件を満たせば最大375万円)。
このように自己負担額を大幅に圧縮できるため、資金繰りに余裕がない中小企業でもECサイト構築に踏み切りやすくなります。
補助金があることで銀行融資に頼る額も減らせ、投資回収の見通しも立てやすくなるでしょう。
オンライン販路拡大による売上増加
ECサイトを開設することで、企業は地理的な制約を超えて新たな顧客層にリーチできるようになります。
従来は地域の店舗来店客や既存取引先に限られていた売上が、オンラインを通じて全国あるいは世界中から注文を受けられるようになり、大幅な売上向上が期待できます。
特に、ニッチな商品や地方の特産品を扱う企業にとって、EC化は販路拡大の大きなチャンスとなるでしょう。
また、中小企業省力化投資補助金の目的自体が「中小企業等の売上拡大や生産性向上」を図ることにあります 。つまり、ECサイトへの投資は単に業務効率化だけでなく、売上拡大にも直結するため、補助金の理念に合致した有効な取り組みと言えます。
補助金の支援によって初期費用の負担を抑えながら新たな販路を開拓できれば、事業全体の成長スピードを加速させることが可能です。結果として、補助事業終了後も持続的に売上を伸ばし、企業の収益基盤の強化につながるでしょう。
業務効率化による人手不足解消
ECサイトは、人手不足に悩む企業にとって強力な解決策となりえます。オンライン販売を導入すれば、これまで店舗やオフィスでスタッフが対応していた販売・注文受付業務の一部を、Webサイトが肩代わりしてくれるからです。
また、営業時間外や定休日でもECサイトは24時間稼働し続けるため、限られた従業員数でも機会損失なく受注を獲得できるようになります。たとえば、従来は閉店後に受けられなかった注文が深夜のうちに入り、翌営業日にスムーズに対応できるといった効果があります。
電話注文や対面接客が減ることで従業員の負担も軽減され、接客に割いていた時間を他の業務や顧客フォローに充てることが可能です。人手不足で一人ひとりの業務負荷が高まっている場合にも、EC化によって業務の一部を自動化・省人化することで、従業員の負荷分散につながります。
補助金によりこうした取り組みが実現しやすくなれば、人手不足の中小企業にとって大きな助けとなるでしょう。
IT導入補助金で対象外となったECサイトも支援対象
2024年度以降、IT導入補助金ではECサイトの構築費用が支援対象から外れました。これまでECサイト開発にIT導入補助金を利用していた企業は新たな支援策を探す必要があるため、中小企業省力化投資補助金がその有力な選択肢として注目されています。
中小企業省力化投資補助金は、人手不足の解消や業務効率化を目的に、ITシステム開発など幅広い投資を補助対象とする仕組みです。
ECサイトも「オンライン販売で業務を省力化する取り組み」として扱われ、サイト制作から受注管理まで広い範囲を補助対象に含められます。
実際、在庫管理や顧客情報の自動連携など、EC化を通じて大きく負担を減らせる事例も想定されるため、IT導入補助金の代わりに中小企業省力化投資補助金を活用する企業が増える見込みです。
中小企業省力化投資補助金の申請要件

ここからは、中小企業省力化投資補助金の申請要件について、以下の点を解説します。
- 補助対象となる事業者(企業)
- 補助対象となる経費・取り組み
- 申請に必要な基本要件
- 賃上げ特例を利用する場合の条件
ECサイト構築は販売チャネルの拡大であると同時に、業務プロセスのデジタル化による省力化効果が見込まれるため、本補助金の対象事業としても適切でしょう。
補助対象となる事業者(企業)
中小企業省力化投資補助金は、日本国内で事業を営む中小企業や小規模事業者が主な対象です。具体的には、中小企業基本法で定める業種別の「資本金」「従業員数」の要件をクリアする法人・個人事業主が該当します。
また、常時使用従業員が5人以下(商業・サービス業の場合)や20人以下(製造業その他の場合)の事業者は、小規模企業者として扱われるケースがあります。
下記は、業種別の一般的な基準例です(※簡略化した一例であり、詳細は公的機関情報をご確認ください)。
| 業種 | 資本金要件 | 従業員要件 |
|---|---|---|
| 製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 1億円以下 | 100人以下・50人以下など |
これらに加え、経営難に直面している企業であっても、中小企業再生支援協議会のサポートを受けながら再建を目指す場合は申請対象となることがあります。
一方で、いわゆる「みなし大企業」や反社会的勢力と関連のある事業者は除外されるため要注意です。
申請前に自社の法人形態や従業員数を確認し、基準を満たすかどうか早めにチェックしておくとスムーズでしょう。
補助対象となる経費・取り組み
中小企業省力化投資補助金は「生産性向上」や「省力化」に直結する投資が支援の中心です。たとえば、店舗や工場に配置する自動化機器、RPAツールを活用した業務効率化ソフト、あるいはECサイトのバックエンドを自動化するシステム開発などが含まれます。
取り組み方は大きく二つに分かれ、事務局が提示する「カタログ型」と、自由度の高い「一般型」が存在します。
【カタログ型】
- あらかじめ事務局が認定した汎用製品を導入する方式
- 清掃ロボットや無人搬送車などの機器購入費・設置費用が対象
- 手続きが簡易で、導入しやすいという特徴あり
【一般型】
- 自社の業種・規模に合わせたオーダーメイド投資を支援
- 開発委託費や新規システム導入費用、クラウド利用料など広範な経費に対応
- 大規模な設備投資も行えるが、公募期間や審査に時間がかかる場合が多い
ECサイト構築も「バックオフィスの効率化」や「受注・顧客管理の自動化」に貢献できれば、補助対象として認められやすいです。
ただし、純粋な広告費用や運用後の更新費などは補助対象外になりがちなので、要件をしっかり確認しましょう。
申請に必要な基本要件
この補助金では「設備導入で省力化を図る」というだけでは不十分で、生産性向上と賃上げにコミットする事業計画を示すことが求められます。
たとえば、ECサイトを構築して受注・発送業務を自動化し、従業員1人あたりの売上を3年で○%アップさせるといった具体的な目標設定が大切です。
さらに、労働生産性や売上総利益の改善を原資として、従業員の給与支給総額を一定水準以上増やす必要があります。「地域最低賃金+30円以上を維持」「給与支給総額を年平均で数%アップ」など、補助金の募集要領に記載の目標を満たす意欲的な計画が必須です。
こうした要件をすべて満たせない場合、たとえ設備内容が省力化に有効であっても不採択となる可能性があります。事業計画書には導入効果の数値試算や賃上げのロードマップを具体的に盛り込んでください。
賃上げ特例を利用する場合の条件
中小企業省力化投資補助金には「大幅賃上げ特例」と呼ばれる追加支援策があります。
これは、通常よりもハードルが高い賃上げ計画(たとえば給与支給総額を年平均6%以上増やすなど)を達成すると約束し、その実行を見込んだ場合に補助上限額をさらに拡大できる仕組みです。
具体的には、従業員が5名以下の企業でも最大1,000万円、20名以下なら最大2,000万円に上限がアップするなど、大きなメリットが用意されています。
もっとも、特例要件を達成できなければ、差額分の返還が求められる恐れがあります。計画倒れを回避するためには、自社の売上アップや生産性向上の見通しを踏まえ、確実に実行できる範囲の賃上げを設定することが重要です。
特例を活用して補助額を増やすかどうか、経営陣の意思決定や財務状況をじっくり検討し、無理なく行える計画を策定しましょう。
中小企業省力化投資補助金を使ったECサイト制作の流れ

実際に、中小企業省力化投資補助金を使ってECサイトを制作するには、以下の手順を踏まえます。
- 事前準備
- 交付申請と審査
- 補助事業の実施(ECサイト構築)
- 実績報告と補助金の受領
これらの手順について、詳しく解説します。
事前準備
まずは、公募要領や公式Q&Aを入念に確認しましょう。ECサイト制作でも在庫管理や決済連携などにより省力化が期待できれば、補助対象となるケースが多いです。
次に、応募のタイミングを把握するため「公募開始日」と「締切日」をチェックし、逆算して書類作成や見積取得のスケジュールを立ててください。
申請時は電子手続き(jGrantsなど)を用いるため「GビズIDプライム」のアカウントが欠かせません。取得には郵送などで時間を要する場合があり、直前になって慌てないよう余裕を持って申請を進めましょう。
さらに、ECサイトの構想やシステム要件を制作会社に相談して見積書を取り寄せ、事業計画書に落とし込む手順を忘れないでください。これらをしっかり準備しておくと、交付申請をスムーズに進められます。
交付申請と審査
準備が整ったら、電子申請システム(例:jGrants)で交付申請を行います。必要書類としては、以下のようなものが代表的です。
- 事業計画書:ECサイトを導入する目的、省力化や売上向上の見込み、賃上げ計画などを明記
- 見積書:制作会社やシステム開発業者から取得した詳細見積
- 決算関連書類:直近の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)など
- その他:GビズIDの登録情報や企業概要、賃上げの根拠資料など
審査では形式要件を満たすかどうかの確認に加え、事業の有効性や実現性が厳しくチェックされます。
「ECサイト構築で具体的にどれほど作業負担を減らせるのか」「賃上げ原資をどのように捻出するのか」といった点が焦点です。審査には数週間から数ヶ月かかる場合があるため、余裕を持って提出し、補足説明が求められた際に即対応できる体制を整えておきましょう。
▼あわせて読みたい
失敗しないECサイト制作!制作手順や費用相場・おすすめ制作会社を徹底解説
補助事業の実施(ECサイト構築)
採択通知後、正式に交付決定の手続きを経てからECサイト制作をスタートします。交付決定日より前に発注・契約・支払いを行うと、その分の費用は補助対象外となるため要注意です。
実施期間は原則として「交付決定日から12か月以内」です。想定以上に仕様変更や開発トラブルが発生するとスケジュールに遅れが生じます。日程管理を徹底し、必要に応じて事務局に変更申請を行いましょう。
制作会社との打ち合わせでは、サイトデザインだけでなく、在庫管理システムや決済機能など省力化につながる要件を明確に盛り込みます。
導入後は受注処理がどれだけ短縮されたかを定量的に測ると、事後報告や生産性向上の効果検証に役立ちます。最終的に納品されたECサイトはテスト運用を行い、機能が正しく動作するかしっかり確認しましょう。
実績報告と補助金の受領
ECサイトが完成したら、補助事業が無事終了した旨を実績報告によって事務局へ届け出ます。実績報告書には、次のような書類をそろえて提出するのが一般的です。
- 経費関連書類:領収書、請求書、振込記録、契約書など
- 導入成果の証拠:完成したECサイトのURL・スクリーンショット、テスト運用結果レポートなど
- 生産性向上・賃上げ状況:申請時に掲げた数値目標(例:受注数増、作業時間削減率)をどこまで達成したかを示す資料
事務局はこれらの内容を精査し、計画どおりの支出・実施が確認できれば補助額の最終確定を行います。
その後、確定額の通知を受領し、指定口座へ補助金が振り込まれます。初期費用の全額を立て替えている場合は、ここで負担が大きく軽減される仕組みです。
書類に不備があると審査が長引く恐れがあるため、領収書や契約書をきちんと整理し、報告期限を守るように心がけましょう。
ECサイト構築に中小企業省力化投資補助金を使うときの注意点

ECサイト制作に中小企業省力化投資補助金を活用することで、多くのメリットを得られます。しかし、補助金の活用にあたっては、以下の点に注意しておく必要があります。
- 省力化効果の明確化が不可欠
- 補助対象外経費に関する注意
- 交付決定前の着手禁止とスケジュール管理
- 補助金受領後の義務とリスク
これらの注意点について、ここから解説します。
省力化効果の明確化が不可欠
ECサイト構築の補助金申請では「販売チャネル拡大だけが目的」と思われると、審査で評価が下がる可能性があります。
中小企業省力化投資補助金という制度名が示すとおり、本質は業務の省力化・効率化です。そのため、具体的にどの作業をどれほど軽減するのか、数値を示すと説得力が増します。
(具体例)
- 従来のFAX受注をWeb注文に切り替えることで、1日あたり○件の入力作業を削減
- 自動在庫連携により、人手で行っていた在庫確認を一括管理し、誤発送リスクも低減
- お問い合わせ対応のチャット化で電話対応を削減し、平均応答時間を○%短縮
計画段階では「達成可能な目標設定」も重要です。
申請後に計画と異なる運用をしていると判明すると、最悪の場合交付金の返還を求められかねません。事業計画と実運用の整合性を取りながら、省力化効果を明確化してください。
補助対象外経費に関する注意
補助金の対象経費に含めたい項目でも、実際には補助対象外に該当する場合があります。たとえば、ECサイト完成後の運営費や広告宣伝費、SNS連携のコンサルティング費用などは原則として認められないケースが多いです。
人件費や雑費など間接的な経費も対象外になりがちなので、計上する前に公募要領と照らし合わせる必要があります。
【主な対象外例】
- 広告費:チラシ・リスティング広告・SNS広告などのプロモーション費用
- 従業員研修費:スタッフの教育・研修セミナー受講費など
- 事業と無関係の設備費:倉庫とは無関係な改装費や家具費など
- 消費税:税金分は自己負担
グレーゾーンにある経費は、事前に事務局へ質問するのがおすすめです。誤った計上で採択後に減額されるより、先に確認しておけばリスクを減らせます。
交付決定前の着手禁止とスケジュール管理
補助金手続きのよくある落とし穴が「交付決定前に契約や支出を始めてしまう」ことです。審査で採択されても、正式な交付決定が下りる前の支払いは対象外とされるため、投資を急ぎ過ぎないよう気をつけてください。
交付決定の通知が届いたら、改めて業者との契約や発注を交わし、そこからECサイト制作を進めましょう。
また、事業実施期間には上限(おおむね12か月前後)があるため、プロジェクト管理を徹底する必要があります。想定以上の時間がかかると追加で手続きが必要となり、最悪の場合、計画未達や報告期限の超過が懸念されます。
さらに補助金は後払い方式のため、開発費全額を一時立て替える余力があるかも重要です。資金繰りの見通しを立てておかなければ、途中で資金不足に陥るリスクが高まります。
補助金受領後の義務とリスク
補助金を受領した後も、補助事業で実現した省力化や賃上げ計画の効果を適切に維持する必要があります。
特に「大幅賃上げ特例」を利用している企業は、事業完了後のモニタリング(数年スパン)で給与支給総額が当初計画を下回らないかチェックされる場合があります。未達成が判明すると、上乗せ分の補助金を返還するリスクが生じるので注意しましょう。
また、税金が原資となる公的資金なので、不正受給や目的外利用は厳しく取り締まられます。虚偽報告や偽造書類が発覚すれば、全額返還はもちろん、将来の補助金申請が制限される恐れも大きいです。
さらに、補助金で導入した設備・システムは一定期間自由に売却や譲渡を行えない場合があり、早々に処分すると補助の趣旨に反すると見なされることがあります。こうしたルールを守り、補助事業で構築したECサイトを長期的に活用してこそ、企業の省力化と成長に結びつきやすくなります。
補助金の活用には事前準備が大切

中小企業省力化投資補助金は、ECサイト構築に伴う大きな費用負担を軽減しつつ、生産性向上や賃上げを促すための力強い助っ人です。
従来は資金面のハードルからオンライン進出を諦めていた事業者も、補助金の後押しでスムーズにEC化へ踏み切れる可能性があります。また、ECサイトは売上拡大や新たな顧客層へのアプローチだけでなく、受注業務や在庫管理を自動化して現場負荷を和らげる効果も期待できます。
ただし、補助金を得るための手続きは多岐にわたり、事前の情報収集や計画策定が欠かせません。交付決定前の支出が対象外になる点や、賃上げ要件・省力化要件をきちんと満たす必要があることなど、押さえるべきルールがいくつもあります。
さらに、受領後も報告義務や設備の活用義務が続きます。こうしたルールを守りながらECサイトを活用すれば、人手不足やコストの課題を乗り越え、持続的な成長に向けたデジタル基盤を築けるでしょう。